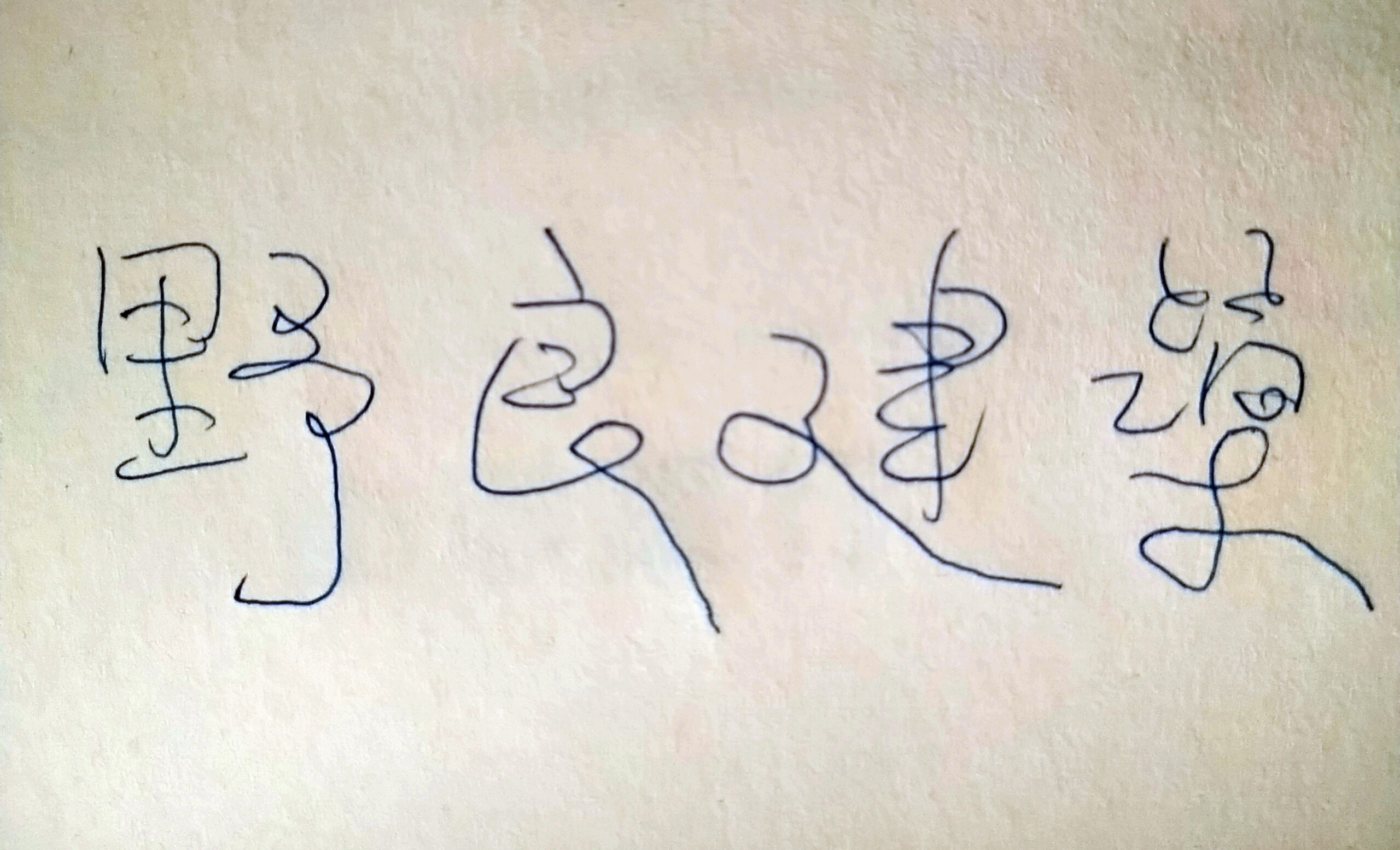春の雨は好きだが、梅雨が嫌いなわけであって、梅雨が好きな人が誰かいるなれば友達になって好きな理由を教えてもらいたい。
あと寿司職人の友達が欲しいと常日頃思う。
夕方だと湿度も少し下がった感じするので材料搬入する。
パワコメ(パワーコメリ東根店)で超軽量石膏ボードを見つける。
普通の石膏ボードの75%軽い。
いちいち重い石膏ボードを運ぶのが苦手な作業なので買おうか迷う。
防火認定はまだ取ってないらしくフラット35を組む様な現場では使うのが難しいが自分の様な作り方をしている人間に相性がいい。
だが値段は普通石膏ボードより1.2倍くらい高い。
0.75の1.2….あー、 どうしよう、
散々迷ったが筋トレだと思って普通石膏ボードを運ぶ。防水石膏ボードよりはいくぶんか軽い。
自分は使わなかったが、女性がDIYする場合は上記をおすすめしたい。

湿気にやられるか少し心配
付加断熱
内側はまずこれでいいとして、外側は雨が降り込んでしまう前に早く透湿防水シートで被う必要がある。
外壁下地の構造用合板を張り終えたら、ボード断熱材(ネオマフォーム)を張る。充填断熱と同じグラスウールも検討したが「外壁を薄くしたい、軽くしたい」という優先事項があったので採用した。
ネオマは材料としては認識があるが、今まで設計でも採用したこともないので勿論施工したこともない。
ボード断熱材は割れたりするので気を使って施工しよう。
断熱系ハウスビルダーのブログやYouTube、ネオマの施工要領書を見て研究する。
まずは土台廻りと開口部廻りに断熱受け材(60×45)を固定する。ネオマは1,820×910の間物をそのまま使う。その方が精度は上がる。床の断熱で上手くいかなかったところを今回は修正する。

この受け材は、本来施工しなくてもいいようだが自分は廃材転用の目的や断熱材のダレ(経年変化による隙間の発生)、透湿防水シートの施工性も加味して採用した。
2段目まで施工すれば雨掛かり部分は防げるのでそれでよし!とする。
窓廻りはいつも検査に行ってるハウスメーカーの仕様を真似してみる。
最後に施工要領書によると気密テープの施工が必要で一応それにならったけど粘着性も悪く、「このテープ必要か??」と思いながら進める。今後この気密テープは省くかもしれない。

最後に断熱材受け材に合わせて透湿防水シートを貼ってまずは梅雨を乗り切る。
今回思ったのが、外壁廻りを改修する時に
既存外壁が窯業系サイディングか木か鋼板なのかで費用や労力の掛かり方が違ってくる。
既存が窯業系サイディングの外壁だと処分費だけでもばかにならない。